子どもはおかしが大好き。
特に、あめやチョコレートなどの甘い物には目がありません。
隠しても、戸だなや引き出しから勝手に取り出して食べてしまうこともあります。
でも、食事に影響するくらい食べてしまうのは困りますよね。
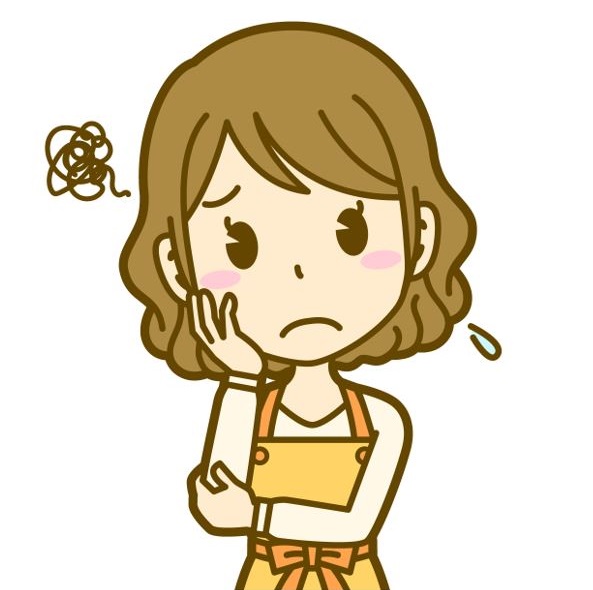
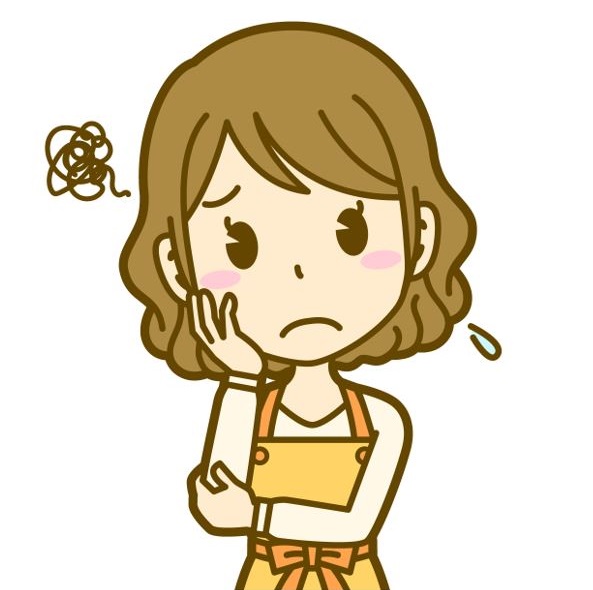
なんてカミナリを落としてしまうこともあるでしょう。
そしてときには、無理やりおかしを取り上げてしまうことも。
ママがこのような態度を取ると、子どもはガマンする気になるどころか、「なんでよ!」と余計に反発するかもしれません。
では、おかしを食べる量を上手に減らしていくにはどうしたらいいのでしょうか。
おかしによる影響を伝える
おかしをたくさん食べると心配になるのは、次のような問題です。
(1)虫歯や肥満になる
甘いものを食べてそのまま放っておくと当然虫歯になります。
また、糖分の取り過ぎは肥満の原因にもなります。
(2)おかしの食べ過ぎで食事が入らなくなる
おかしを食べすぎると、その後の食事が入らなくなることがあります。
ママにとっては、せっかく作った食事を残されるのは悲しいですよね。
それが続くと、ときには「イラッ!」とすることも。
また、普通の食事が食べられなくなると、ビタミンやミネラルなどの成長に必要な栄養が不足してしまいます。
(3)病気になるリスク
糖分を取り過ぎると、インシュリンの調節機能がうまく働かなくなり、低血糖の状態になります。
これにより、子どもは気力がなくなったり、集中力が低下したりします。
また、糖尿病のリスクも上がると言われています。
これらのような影響をわかりやすい言葉でやさしく子どもに伝えてみましょう。
伝える方法は、「おかしを食べすぎると、○○だから心配なの」というように、ママの心配な気持ちを言葉にします。
「おかしにはこんな影響があるんだ」ということや、「ママがこんなに心配してくれているんだ」という気持ちが理解してもらえたら、おかしを食べすぎることが減ってくるでしょう。
おかしを食べるときのルールを決める
おかしを禁止すると、子どもにストレスを与えてしまいます。
ガマンをさせすぎると、余計におかしに執着したり、親に隠れて食べてしまうことも。
お友だちの家に遊びに行っておかしが出されたときに、周りがびっくりするくらい食べていた、なんていうこともあるかもしれません。
まったく食べさせないというのではなく、食べる量をコントロールすることで、上手に対応していきましょう。
そのうえでオススメなのが、「おかしを食べるときのルールを決める」ことです。
親子で一緒に話し合って決めていくとよいでしょう。
たとえば、次のようなルールが考えられますね。
- おかしは食事を食べた後に食べる
- 1日に食べる量を決める
- おかしを食べた後は歯みがきをする
- 友だちが一緒のときは量が増えてもOKとする
食べてよいものだけを用意する
家におかしが置いてあると、つい食べたくなってしまいます。
目の前におかしがあるのに、「これはダメ」と言われても守るのは難しいもの。
であれば、食べてほしくないおかしは、家に置かないようにしてみましょう。
この他にも、おかしを一緒に作って食べるというご家庭もあるようです。
これなら、食べてほしいものを与えることができますね。

